ブログの音楽カテゴリーにいくつか記事をUP予定だった。
主に、3月に予定していたRacco-1000主催イベントと
5月に開催予定だった「フエフケール」の告知のことだ。
また、急遽決定した法螺貝関係のイベント報告も書くつもりだったが、
日を重ねるにつれてコロナ対策の強化を迫られた故に、
試奏体験タイムの設定は厳しいと判断したため中止を申し出た。
日が経つにつれ、コロナ対策は相当の長期戦になることが明らかになった。
芸術系だけでなくスポーツのイベントも軒並み中止または延期となっている。
関係者の生活を思うと胸が痛くなるし、現金給付など補償をしっかり行ってほしい。
しかし、今後も同様に人類が新興感染症に遭遇することはありうる。
グローバルに人が移動するので、今後さらにその確率は増すだろう。
その度に、イベント自粛を繰り返していたらどうなるだろう。
国や地方自治体の補償額が膨大になり、財政的に疲弊するだろう。
(平時の税金の無駄遣い等の話は、他の方が沢山書いているのでここでは触れない)
だからこそ、オンラインでも実施できるイベント等のスタイルを創出し、
未来につなげることが重要だと思う。
私もお流れになった「ホラガイ類トーク」イベントをオンラインで実施検討中である。
ZOOMテストが成功すれば、具体的に企画して告知予定だ。
これは、深刻な感染症流行や災害がない平時でも、
様々なメリットがあるだろう。
都度、交通費を払って大都市に行く必要がなければ、
それだけ、費用が浮いて色々なイベントに参加できるようになり、
イベンターにとってもチャンスが増えるのではなかろうか。
(ホテル、旅館などは遠征減による影響があるかもしれないが、
そういう事業者も遠隔の新サービスを打ち出すのもありだろう)
補足
知恵を絞って、オンライン開催に変更して中止回避ができるケースが大幅に増えれば、
どうやってもオンラインでの開催が難しく、
中止に追い込まれる事業者への補償を手厚く行いやすくなると考える。
しかし、速やかに補償を実施できる制度がなければ意味がない。
そのため、失業保険に近い制度も検討すべきと考える。
例えば、失業保険の適用範囲を一時的に広げ、休業補償にも適応するなどが考えられる。
また、被雇用者だけでなく個人事業主にも対象を広げるべきだと考える。

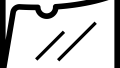


コメント